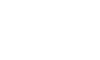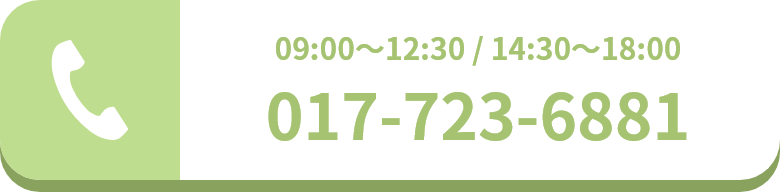肉離れについて
肉離れ(筋挫傷)の概要 ■ 定義 肉離れとは、筋肉が強く引き伸ばされることによって、筋繊維の一部または全部が損傷・断裂する外傷性疾患です。**筋挫傷(muscle strain)**とも呼ばれます。 ■ 好発部位 主に下肢の筋肉に多くみられます: ハムストリングス(大腿後面) 大腿四頭筋(大腿前面) 腓腹筋(ふくらはぎ) ■ 原因・誘因 急なダッシュやジャンプ動作 急停止・方向転換 ウォームアップ不足 筋肉疲労や柔軟性低下 ■ 症状 筋肉部の急激な痛み 断裂部位の圧痛や腫れ 重症例では陥凹の触知や内出血(皮下出血斑) 歩行や運動時の困難 ■ 重症度分類(一般的な3段階) 重症度 内容 回復期間の目安 軽度(Ⅰ度) 筋繊維の微小損傷、痛み軽度 1〜2週間 中等度(Ⅱ度) 筋繊維の部分断裂、腫れや皮下出血あり 4〜12週間 重度(Ⅲ度) 完全断裂、陥凹・高度な痛み 12週間以上〜手術検討 ■ 診断 視診・触診(陥凹や圧痛の確認) エコーやMRIによる筋断裂の評価 ■ 治療 急性期(受傷直後〜48〜72時間) RICE処置(Rest, Ice, Compression, Elevation) 安静・冷却・圧迫・挙上 炎症が強い場合は消炎鎮痛剤の使用 回復期 軽いストレッチ → 筋力トレーニング スポーツ復帰は痛みがなく、筋力バランスが回復した後 重症例 筋腱の完全断裂では手術療法が選択される場合もある ■ 予防 十分なウォームアップとクールダウン 柔軟性トレーニング 適切な筋力トレーニング 再発予防としてのフォーム修正やバイオメカニクス評価