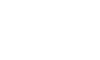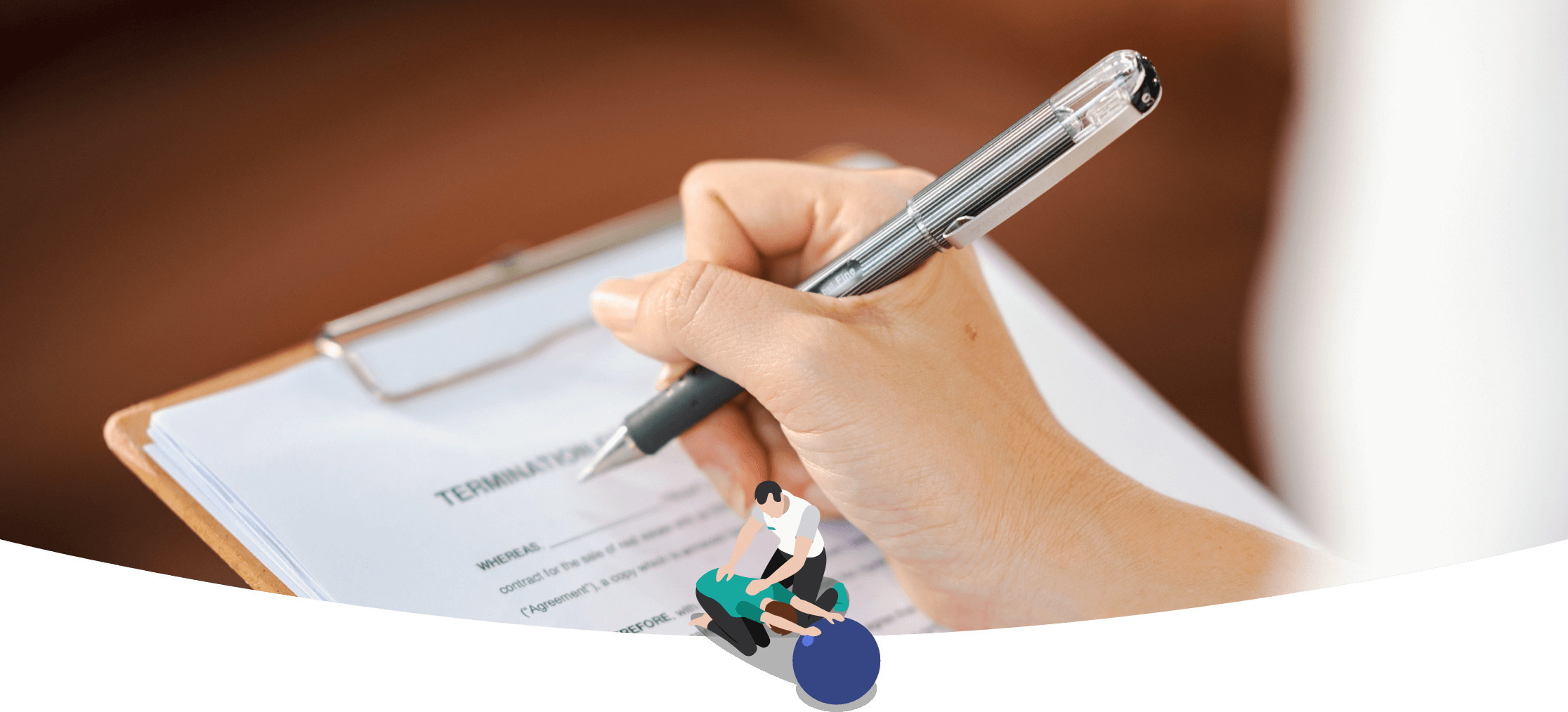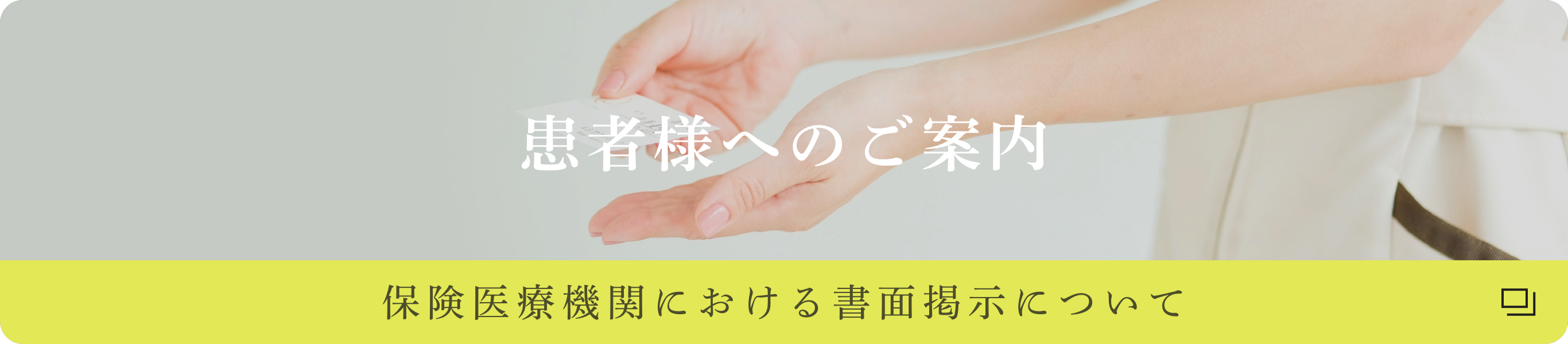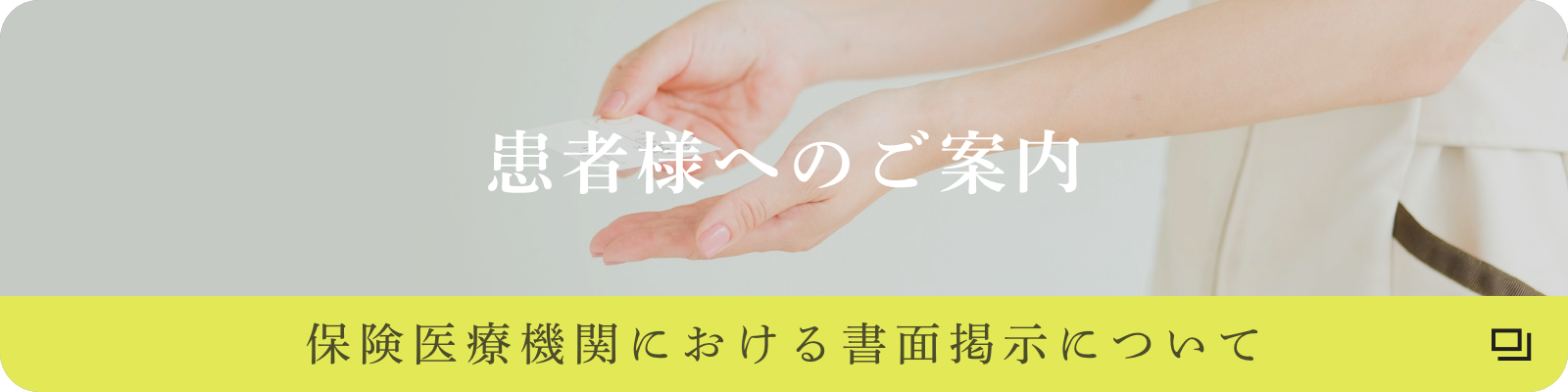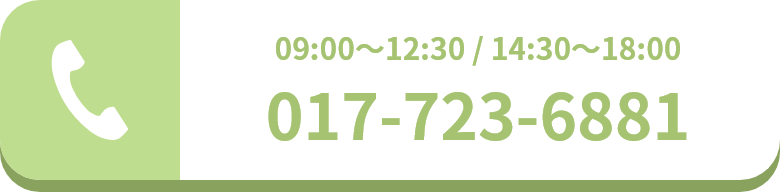よくある質問
- Q.
- 整形外科と形成外科、美容外科の違いはなんですか?
- A.
- 「形成外科」や「美容外科」が「整形外科」と混同して使われることがありますが、これは誤りです。
「形成外科」は、生まれながらの異常や、病気やケガなどによってできた身体表面の異常を改善する(治療する)外科です。 熱傷(やけど)、ケガや手術後の皮膚の瘢痕・ケロイド、生まれつきの母斑(あざ)などは、形成外科で治療できます。
「美容外科」は形成外科の一分野で、いわゆる「美容整形」の手術を行います。容姿を整えることが目的で、代表的な手術には、二重まぶたなど眼瞼の手術、鼻を高くする隆鼻術、顔面のたるみをとるフェイスリフト、腹部や臀部の余分な脂肪を取る脂肪吸引、乳房の形を整える手術、レーザーであざを消す手術等があります。
- Q.
- 整形外科と整骨院では、何が違いますか?
- A.
- 整形外科では、医師(整形外科医)が骨・関節・筋腱(運動器)・手足の神経(末梢神経)・脊椎脊髄の治療を行います。診察による理学所見とX線(レントゲン)やMRI等の検査をもとに診断し、症状や病態に合わせて投薬、注射、手術、リハビリテーション等を行って治療します。
整骨院(接骨院)では柔道整復師が施術を行います。柔道整復師は医師ではなく、あん摩・マッサージ、はり・灸師と同じ「医業類似行為」と呼ばれる資格です。外傷による捻挫や打撲に対する施術と、骨折・脱臼の応急処置は行えますが、変形性関節症や五十肩のような慢性疾患は取り扱うことができません。整骨院では画像診断に基づいて施術することができないため、場合によっては症状を増悪させる可能性があります。
- Q.
- サプリメントを飲んでいますが、効果は期待できますか?
- A.
- 一般にサプリメントとして販売されているものは、科学的データとして有効性が認められていないために保険では認められていません。しかし、まったく効かないというデータもないのです。そのため、現時点でまったく効果がないとも言い切ることができません。
- Q.
- 交通事故の治療期間はどのくらいですか?
- A.
- 3カ月から6カ月経った段階で、保険会社から治療の終了をすすめられることもありますが、まだ症状の改善・回復を見込める場合は、治療を継続することができます。
一方、傷病の症状が安定し、症状の回復・改善がそれ以上期待できなくなった状態(症状固定)と判断した場合は、「後遺症診断書」をお出ししております。症状固定となったら、事故扱いのまま漫然と長期加療することは、おすすめできません。
- Q.
- 交通事故診療における症状固定・後遺障害の考え方
交通事故、労災保険上の症状固定とは?
- A.
「症状固定」は「治癒」と同義であり、次のように定義されています。
「治癒(症状固定)」とは、負傷または疾病に対して、医学上一般に認められた治療を行っても、その「医療効果が期待し得ない状態」に至ったものです。急性症状が消退し、たとえ慢性症状が持続してもその症状が安定し、医療効果がそれ以上期待し得ない状態になったときのことをいいます。
「治療効果が期待できなくなったとき」とは、症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいますが、投薬・理学療法などの治療により一時的な症状回復が認められるに過ぎない場合も含まれます。後遺障害の有無や程度は、労災保険の場合、監督署長が「判断」し、交通事故の場合は保険会社が「認定、決定」します。担当医はあくまで医学的事実に基づいた現状や今後の経過を述べられるに過ぎず、後遺障害の有無・程度を認定する立場にありませんので、ご理解ください。
- Q.
- ジェネリック医薬品とは何ですか?
- A.
- 開発したメーカーが発売する薬のことを「先発薬」といい、先発薬の発売後、数年経過した後に他社が発売する薬のことを「ジェネリック医薬品」といいます。
一般的にジェネリック医薬品は先発薬と効果は同じですが、開発費がかからないので、先発薬より安い価格で処方が受けられます。ジェネリック薬品をご希望、またはもっと詳しく知りたい方は、診察の際にお気軽にご相談ください。
- Q.
- 整骨院、接骨院への通院に紹介状は必要ですか?
- A.
- 整骨院は医療機関ではないため、医療機関は整骨院における施術を必要な治療行為として認めない傾向があります。
整骨院の利用に医師の同意は原則必要とありますが、紹介状は必要ありません。
医師が整骨院の利用を積極的に反対しているような特別な場合を除き、患者が整骨院利用を希望すれば通院は可能です。前述の医師からの同意とは、患者の整骨院、接骨院の利用について消極的に同意する、つまり意義を唱えないといった程度で足りるからです。
但し、整骨院、接骨院で保険適応となるものは、受傷から概ね2週間以内のケガや痛みで、「〇〇をした時に捻って痛めた」など、受傷した原因がわかるものが健康保険の対象となり、それ以外は健康保険の対象外です。
- Q.
- 診断書の作成依頼について
- A.
- 診断書は、会社の休職制度を利用するときや、保険の手続き(保険の場合、保険会社のフォーマットがありますので保険会社へ直接お問い合わせ下さい)をするときなどに必要です。
しかし、診断書は日常的によく使うものではないため、依頼される患者様もどのような診断書をもらえば良いのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そして、診断書の用途によって、記載しなくてはいけない項目や内容が変わってきます。
例1 「この日に受診したということが分かればいい」ケースであれば、日付と病名のみの記載でも問題ありません。
例2 「いつからいつまで就労できないかわかればよい」ケースであれば、これに加え必要な休職期間の記載があれば問題ありません。
例3 「いつから就労可能であることがわかればよい」ケースでは、○月○日より就労可能であるで問題ありません。
しかし、場合によっては、より詳しい内容が分かる診断書を提出しなくてはいけないこともあります。
そのため、診断書の提出を求められたら、どの項目の記載が必要なのか患者様自身に、事前に確認して頂かなければなりません。
診断書に書かれているのは、患者の氏名や住所、受診日や病名などの情報です。
病院やクリニックによって、フォーマット(形式)が異なるケースはありますが、基本的な項目は下記の通りです。事前に会社へご確認ください。
・患者情報(氏名や住所など)
・病名
・発症日
・受診日
・治療内容
・治療の見込み期間
・必要な休職期間
・労働の程度 (就労不可、事務的軽作業のみ可能など)
・症状の経過
・検査結果 など
診断書の用途によって、必要がない箇所は省略されます。
書面による同意確認を行わない
軽微な処置・医行為について
当院では、「書面で同意をいただく診療項目」と「
診療を円滑に進めるために、これらの診療項目については、説明と同意確認を口頭及び院内掲示で対応しております。
1 一般項目
各種問診、視診、身体診察、体温測定、身⾧測定、体重測定、
2 検査、モニター
静脈血採血(※1)(血液学検査・生化学検査、免疫学的検査・
3 処置
静脈血採血、動脈血採血、チューブやドレーン類のテープ固定・
4 投薬、投与
通常の投薬、注射、末梢静脈内留置針挿入(点滴路の確保)、
上記の診療行為は、一定以上の経験を有する医師・看護師・
このような場合は、
(※1)『採血』は、基本的に安全な手技であり、
1 止血困難・皮下出血
穿刺後の不十分な止血操作などが主な原因です。
2 アレルギー
採血時の消毒薬(アルコール)でかゆみ、
3 神経損傷
採血後に手指へ拡がる痛み、しびれなどが生じ、
4 血管迷走神経反射
心理的に緊張、不安が強いと起こりやすいとされ、採血(検査)
※これらの合併症が起きた場合には最善の処置を行います。 何かいつもと違う症状が現れた際はすぐにご連絡いただきますよう
医師、病院の応招義務
※医療機関と患者間の関係が壊れるような(言い合い、
院内における無許可での写真・
当院では、
許可なく撮影等を行っていることが判明した場合は、